横、縦、奥行き!XYZ軸を使うゲームの考え方(地上戦・空中戦)
3Dゲームでは、X軸、Y軸、Z軸という形で、3つの軸が存在しますが、意外にこの3つの軸を自由に使ってプレイ出来ているゲームは少ないです。
これはなぜかというと、この3つの軸を全部解放してしまうとゲームとして複雑怪奇なものになってしまうからです。
参考例として私が実況しているゲームですが、『ボーダーブレイク』と『スターウォーズ スコードロン』を出して説明します。
ボーダーブレイク
移動できる軸を考えてみる。
ボーダーブレイクの軸制限は下記となります。
- ジャンプはブースターが切れるまで(Y軸に制限)
- マップの広さの制限はあるが移動は自由(X軸とZ軸の移動制限はない)※1
※1 マップ外に出ると死亡となりますが、マップ内では、移動制限がないため
スターウォーズ スコードロン
移動できる軸を考えてみる。
スコードロンの軸制限は下記となります。
- 宇宙戦のためか、移動軸の制限はない ※2
※2 マップ内であれば、XYZ軸制限なく移動することができる。
3つの軸が鍵

3つの軸を自由に使えるスターウォーズは、優秀そうに見えますが、そうではありません。
ゲームとして動ける軸の制限をなしにした場合には、複雑な考えをしなければならなくなりプレイヤーに注意しなけれならない箇所が増えます。
3軸はストレスが上がりやすい
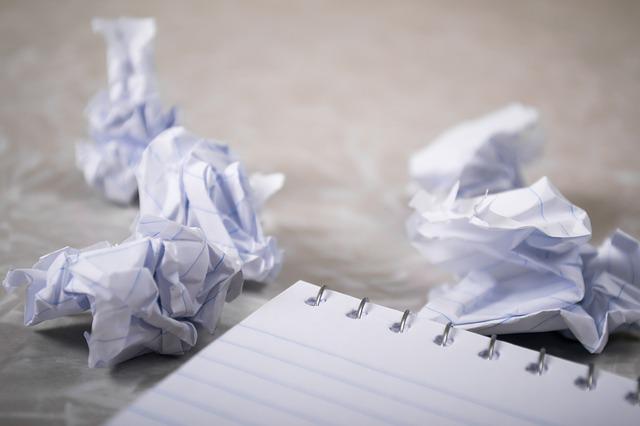
3軸の場合、現実に近い形となりますが、空間認識力が必要になりますし、なおかつ人が常日頃空中を飛んでいるならまだしも、地面を歩いて生活をしているので、その中で高さの概念を考えながら進むとなるとストレスを受けやすくなります。
スパイス的な要素
3軸を使う場合は、スパイス的な要素としていれるのが良いです。
アクションゲームなどで取り入れる場合は、あくまでも制限がある状態にすることが望ましいです。
『ファイナルファイト』や『天地を喰らうⅡ』など、跳躍力は、実際にはありえないぐらいのジャンプですが、ジャンプ攻撃や飛び越えたりなど、スパイス的な要素にできます。(※Bloodstainedを追加、悪魔城ドラキュラのような感じのゲームです。)
天地を喰らうⅡ
Bloodstained
2軸までの使い方が重要
X軸とZ軸のみの場合、敵の攻撃が来た場合、その位置をパッと確認することができます。
実際に自分の視界内で、何か起きた場合は、その場所がパッとわかると思います。
しかし、ここにY軸が増えると、途端に視界内に入ったとしても、それが今いるところと同じなのかを計算する必要があります。
この1手が実は、非常に労力を使います。
アクションゲームで、左右に移動する敵を狙うのと、左右移動しながらジャンプする敵を狙う場合、後者の方が狙いにくいです。
シンプルに考えることをさせるゲームにする必要がある

今回、このXYZ軸を使った場合の戦闘では、
空中戦が考えられますが、この空中戦は、如何にこの3軸目を感じさせないかがプレイヤーにとっての負担とゲームへの集中へのポイントとなります。
もちろん、複雑な動作の方が楽しいというプレイヤーもいると思いますが。
大抵がそうではありません。
複雑な動作のゲームが100万本売れるかというとそれを目指す方が相当難しいので。
最初の10分が重要
プレイヤーに遊ばせる際には、最初の10分がカギとなるため、その10分間にどれだけこのゲームが楽しいのかを伝える必要があります。
複雑であれば、あるほどこの10分間の中で説明で終わってしまうため、離れてしまうプレイヤーが多いでしょう。
ゲームを制作していると、どんどん色々なものを追加してしまいがちですが、一旦整理して、ゲームのコアとは何なのかを今一度考え、プレイヤーを楽しませるというのを考えてみて下さい。
XBOXで『鉄騎』というゲームが
余談ではありますが、複雑化という点では、『鉄騎』というゲームは、男の子心をくすぐることをやってはいました。
私も購入してパイロット風の椅子とかテーブルとか用意しましたが、正直、購入したときと始まる前のワクワク感は非常に強かったです。
わざわざ専用のコントローラーとか作って、脱出ボタンとか専用にあるってのは、浪漫です。
ですが、このゲーム1戦やると、正直めっちゃ疲れるんですよ…。(学生時代で、ゲーム数時間プレイとか当たり前の時に1戦やるとお腹一杯になり精神がなくなるレベルです。)
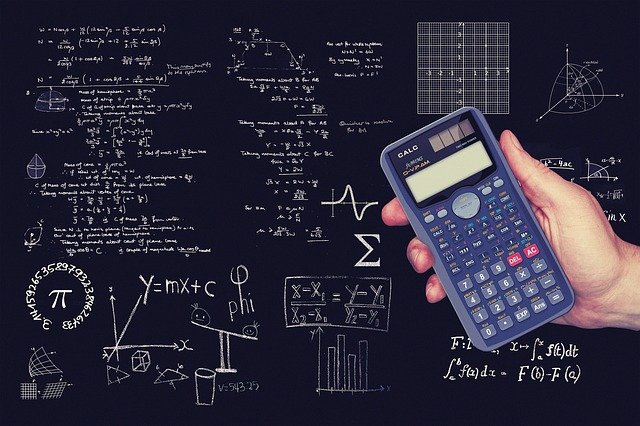


コメント